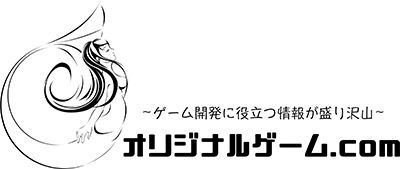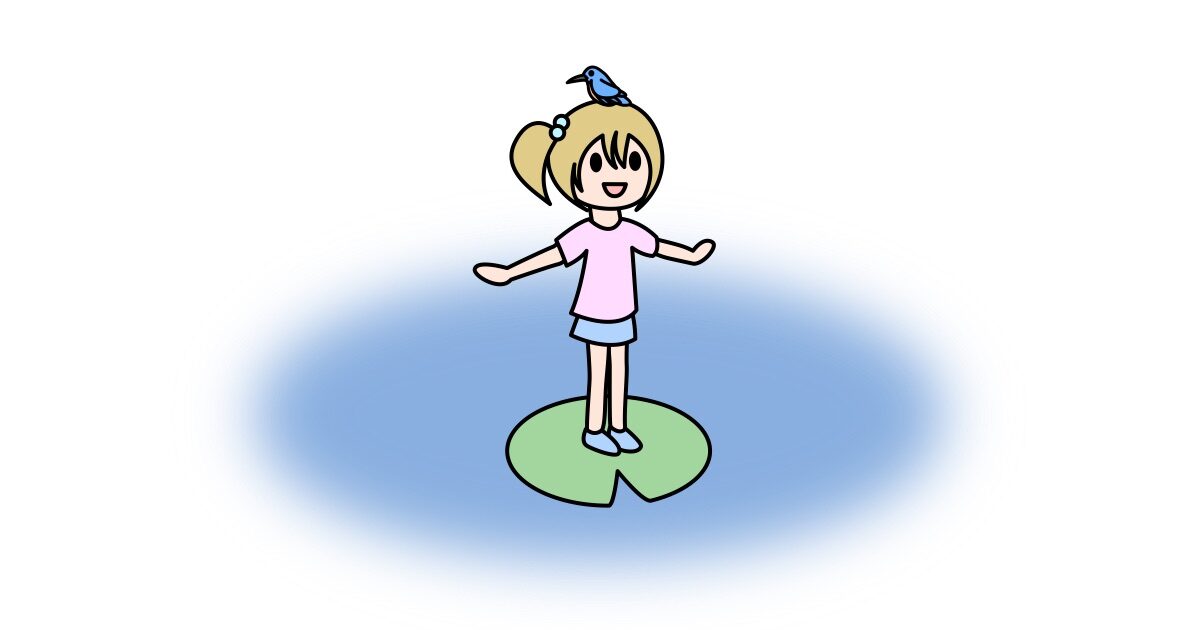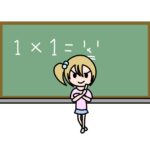Pythonプログラミングにおいての、if文の使い方を学んでいきましょう。
if文の使い方
Pythonプログラミングにおける条件分岐では、if文というものを使って、コンピュータさんにお願いをしていきます。if文というのは、「はい(True)」か「いいえ(False)」かによって、コンピュータさんに違うお願いをすることができるものです。
では、こちらのソースコードをご覧ください。
is_true = True
if is_true:
print('Trueです')これは、is_trueがTrueならば、Trueと表示するプログラムです。
(Falseのときはなにも表示しません)
条件分岐は、3〜4行目で行なっています。
「if is_true:」というのが、条件を分岐させるもので、「もし、is_trueがTrueならば……」という意味になります。
ここでの注意点として、後ろのコロン(:)を忘れないようにしましょう。
さて、この条件がTrueのときのお願いは、次の行の最初に「空白」を入れて、書いていきます。
空白は、基本的に「スペース4つ」にします。

1行目で、is_trueにTrueを代入しているので、実行すると「Trueです」と表示されます。
実行結果
Trueです
if文を使ってみよう!
では、if文を使って、「ゲームのスコアが80点以上ならば、おめでとう、と表示する」というプログラムを作ってみましょう。
score = 90
if score >= 80:
print('おめでとう')実行結果
おめでとう上のソースコードの3〜4行目をご覧ください。
「score >= 80」というのは、「scoreが80以上」という意味です。
「>=」は、比較演算子のひとつで、今回の場合は、scoreが80以上ならば、「はい(True)」と答えてくれます。
(くわしくは「比較演算子」をご覧ください)
そして、1行目でscoreに90を代入しているので、「score >= 80」は「True」になります。
ですので、4行目の「print('おめでとう')」というお願いを、コンピュータさんが見た、ということになります。