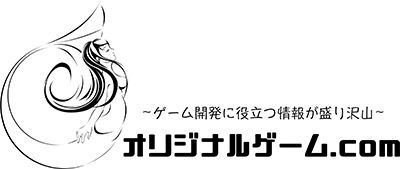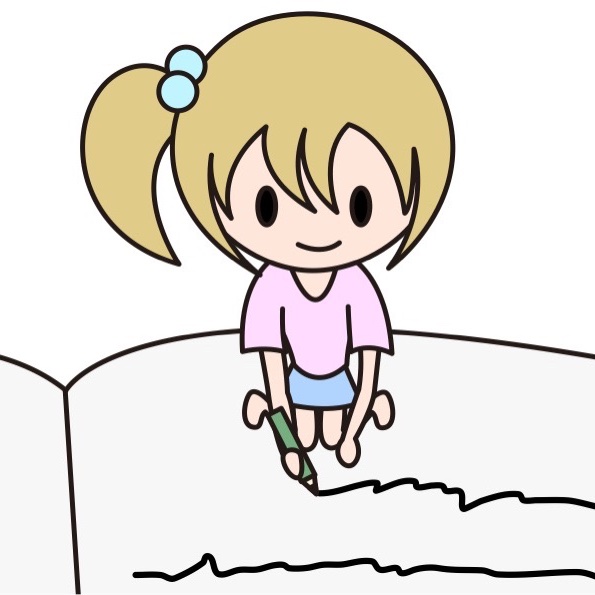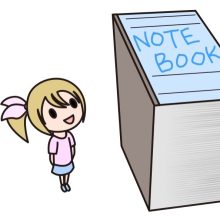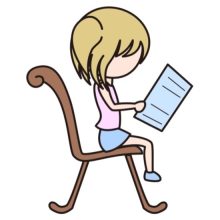RAM(Random Access Memory)は、いろんなことを一時的に覚えておいてくれるメモリのことで、メインメモリと同じ意味です。
RAMとは
RAMは、ハードディスクやSSDから読み込んだものを、一時的に覚えておいてくれるものです。
メインメモリと同じ意味で使われます。
たとえば、みなさんはノートに書き込んで、いろんなことを覚えているとします。
そのノートを、ちょっと手直ししたいな、と思ったとき、そのノートを読んで、なにをノートに書き込むかを頭のなかでまとめて、それからノートを直しますよね。

この、頭の中に一時的に記憶しておく、という役割をしてくれるのが「RAM」です。
そしてノートは、SSDやハードディスクといった、「ストレージ」に当たります。
もっとくわしいRAMの説明
「RAM」は、スマホやパソコンの「メインメモリ」のことです。

メモリというのは、このメインメモリ以外にも、メモリっぽいものがたくさんあります。
USBメモリとか、メモリーカードとか、そういうものです。
しかし、USBメモリやメモリーカードといったものは、RAMではなくストレージです。
USBメモリ、メモリカード、SSD、ハードディスクなどは、ストレージの仲間です。
これらは、スマホやパソコンの電源を切ったり、取り外したりしても、データが消えることはありません。

しかし、スマホやパソコンのメインメモリ、つまりRAMは、パソコンやスマホの電源を切ると、データは消えてしまいます。
でも、ストレージよりRAMの方が、たいていの場合は速いです。
では、ストレージとメインメモリの関係を、パソコンの場合を例に、かんたんに説明します。
パソコンのデータは、SSDやハードディスクなどの、「ストレージ」に保存されています。
ストレージは「ノート」と考えると分かりやすいです。
最近のストレージは、たくさん書き込めるので、とっても分厚いノートです。

こういったストレージの多くは、読み書きが遅いです。
分厚いノートから、目的のページを探して、消しゴムで消して、鉛筆で書き直す、というふうなイメージです。

そして、そのノートから目的のページを見つけたら、とりあえずいまだけでいいので、内容を覚えてしまっておきたいですよね。
だって、内容を覚えてしまわなければ、なんどもそのページを読み直さなければいけなくなってしまいますから。
そこで、ストレージから読み込んだものを、一時的に覚えておいてくれるものがあります。
それが「RAM」、つまり「メモリ(メインメモリ)」です。

ノートに書き込んであるものを直そうとしたとき、考えたことをすべてノートに書き込んでいくとしたら、とっても大変ですよね。
おそらくみなさんは、ノートを読んで、頭の中でなにを書くべきかまとめて、それからノートに書き込むと思います。
それと同じで、どういったものを書き込むかまとめる、つまり頭の整理をする、といったことが、このメモリ上で行なわれます。
つまり、メモリ上で、どういったものを書き込むのかをまとめてから、それをノートに書き込むので、何度もノートを読み直したり、何度も消しゴムで消して鉛筆で書き直したり、といったことをしなくてもよくなります。
ですので、その分、動きがスムーズになります。

ではここで、具体的な話をしてみましょう。
たとえば、ハードディスクに保存された、テキストデータを開いたとします。
するとまず、ハードディスクにあるそのテキストデータを、メインメモリが記憶してくれます。つまり、開いたテキストデータは、いまはメモリにコピーされている、ということになります。
そして、テキストの編集はメインメモリの上で行なわれます。
編集が終わってそのテキストデータを保存したとき、メインメモリが覚えておいてくれた編集後のデータが、ハードディスクに保存されます。
これが、パソコンでデータを書き換えるときの流れです。
また、RAMとよく似た言葉に、ROMというものがあります。
ROMは「Read Only Memory」を短くしたもので、「読み込みだけのメモリ」という意味です。
アーティストのCDや、ゲームソフトのディスク、映画のBlu-rayなどが、ROMと呼ばれるものです。
RAMとROMは、文字としてはとても似ていますが、実際はまったく違うものです。
RAMが一時的な記憶なのに対して、ROMを例えるならば、本です。
消すことも、書き込むこともできません。ただ、読むことしかできないものです。

まとめ
RAMは、SSDやハードディスクなどのストレージから読み込んだものを、一時的に覚えておいてくれるものです。
スマホやパソコンに入っているメモリ(メインメモリ)とRAMといいます。
ストレージは、スマホやパソコンの電源を切ったり、取り外したりしても、データは消えません。
しかしRAMは、スマホやパソコンの電源を切ると、データが消えてしまいます。
ストレージに保存されたものを、いったんRAM(メインメモリ)が覚えてくれて、そこで編集するという仕組みにすることで、スムーズにスマホやパソコンを操作することができるようになっています。